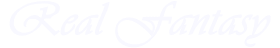Real Fantasy物語 ~勇者ジェミニの伝説 外伝~ -光と影の物語-

2025-11-15
元になるお話はこちらから
「勇者ジェミニの伝説 クリスタル探索冒険記 -アレーシャの森編ー」
世界に名を轟かせる、光の騎士たちが躍動する国、バルドティア王国。
その国を建国した、1人の騎士が名声を手にし、人の暖かさを知り、そして苦しみと悲しみに堕ちた、人生の物語。
10歳の時だった。
自分が特別だと気づいたのは。
元々魔法も剣術も得意だった。
特に光魔法については、物心ついたころから自由に使うことができた。
私が8歳のころ、魔物に襲われたとき、必死にその脅威から逃れるために剣に光の魔法をまとわせて戦うことで魔物を退けることができたんだ。
それを機に、私は同様の戦い方を無意識のうちに行うようになっていた。
「バルドス。驚いた、どこでそんな技術を覚えたんだい?剣に魔法をまとわせるなんて、初めて見たよ。」
「先生!魔物から逃げようとして必死だったから僕にも分からないんです。でもこうすると、すぐに魔物を倒せちゃうんですよ?すごいでしょ、先生!?でも、すごく疲れちゃうけど。」
「うん、すごいよ、バルドス。君は特別な子だね。でもその技にはあまり頼らないことだ。強すぎて剣技を磨くことに油断が生まれてしまう。剣は剣の技術として、魔法は魔法の技術として磨くことに専念しなさい。」
先生がどうしてそんなことを言うのか私には分からなかった。
どうして強い技に頼ってはいけないのか。そのほうが魔物にも人間にも負けないのに。
そして何よりその技術は、身寄りのない私が周囲から大いに認めてもらえる数少ないきっかけでもあった。私は先生からの警告もそこそこに、剣に魔法をまとわせる技術に心酔していった。
しかし、先生の教えは正しかった。後にあんなことになるのだから。
周りの子たちも、大人たちも、誰も私の真似ができない。
自分は神から大きな運命を授かって生まれたのだと、そう思った私は剣に魔法をまとわせる技術を磨いていった。
火の魔法、水の魔法、氷の魔法、風の魔法、闇の魔法、いろいろと試してみたがどれも思うようにはいかなかった。結局、光の魔法と剣を組み合わせた魔法剣を自分の技として磨きをかけていき、15歳の頃にソルミナ王国護衛団に入団した。
そのころには私はちょっとした有名人になっていた。入団前の数年、同じ門下生の友人たちとチームを組んで魔物の討伐に出て、功績をあげていたのだ。
「おい、聞いたか。あの噂の光の魔法剣士がうちに入団するらしいぞ。」
「ああ、聞いた聞いた。西の魔物の巣窟を一掃したそうだな。俺も魔法剣教えてもらおうかな。」
「なんだ、ただのガキだろ?ちょっと功績をあげただけじゃないか。そんなんで護衛団の任が勤まるかよ。」
「ははは、お前よりもよっぽど役に立つかもな。」
様々な声が聞こえてはきたが、気にはならなかった。
なぜなら私はそのどの者よりも自分のほうが強いという自信があったからだ。
実際に入団してわずか1年で、護衛団の小チームのリーダーを任されるようになった。
魔法剣を習いたいという者が後をたたなかったが、無意識で使っていたため自分でもどうすれば使えるようになるのかが分からなかったのだ。
少しずつ私の名も世間に知られるようになっていき、隣国の護衛の依頼を受けることも次第に増えていった。
「お父様、今度のヴァルグレア帝国での晩餐会への護衛はバルドスでお願いね!」
「すまないレイティア、その日彼には別の任務を依頼しておるのだ。」
「いやよ!だったら晩餐会には行かないわ!スヴェット相手だとちっとも楽しくないんだもの。」
「そう私を困らせないでおくれ。どうにかできないか掛け合ってみるから……。」
ソルミナ王国には私と年の変わらない姫がいた。
同年代ということもあり、姫は私に気さくに話しかけてくれた。
何度か遠征の護衛の任に就く中で、私たちは次第に打ち解けていった。
「ねえ、バルドス。あなたは最近他の国の護衛に行ってばかりね。私のお話相手がいなくてつまらないわ。お父様は護衛団を強化して隣国との取引で国を大きくしようとしてるみたいだけど、私はそんなの興味ないのよ。断ってちょうだい。」
「ははは、姫様。国の繫栄は我が国王陛下の偉大なる意思。その繁栄で民の暮らしを豊かにしようとお考えなのだと思います。そして何より姫様をお守りする力もより強くなります。」
「私はそういうの好きじゃないわ。だって強くなったって幸せになるとは限らないでしょ?私はね、みんなが笑顔で暮らせる国になって欲しいの。もちろんそのためには魔物にそれを脅かされない強さも確かに必要よ?でも、強さはあくまでも守るための1つの手段よ。強さなんて求めてもキリがないわ。強さで発展しても、それはさらなる強さの脅威や不安を招くだけだもの。そんなことじゃなくて、あくまでもみんなが笑顔でいられるかどうか。それが大事だと私は思うの。とにかく!お父様からの他国の護衛の任は全部断って!」
「し、しかし、さすがに私からは陛下には……。」
「いいわ、私がお父様に言うわ!」
「姫様、あまり陛下に厳しく当たられると、陛下も落ち込んでしまわれますよ。」
「いいのよ。お父様は私のことなんてちっとも気にかけていないんだから。それにいつまでも子ども扱いするのよ!お母様だっていつもお父様の肩を持つんだから。」
「しかしついこの前も陛下と王妃様が、姫様のお話を楽しそうにしていらっしゃいましたよ。次の姫様の生誕祭は盛大に執り行いたいと聞こえてまいりました。」
「あ、そうだ!バルドス!次の生誕祭の私のダンスの相手はあなたにお願いするわ!」
「ええっ、わ、私は、舞踏の心得が全くないのですが……。」
「だったら私が教えてあげる!」
「いつも他の国の王子たちと踊ってるけど、みんなヒョロヒョロしてて頼りないのよね。うんうん、いいアイデアだわ!すぐにお父様にお願いしてみるわ!」
「は……はい!」
とても明るく率直で笑顔の絶えない姫の存在は、自国、他国ともに緊迫感の強い護衛が続く私にとっては心安らぐ時間だった。
そして私が18歳のころ、護衛団の副団長を任されることになった。
異例の速さでの要職だった。
さらに時期を同じくして、私はレイティア姫との婚姻が決まることとなる。
「すまないな、バルドス。うちの娘がずいぶん君を振り回したことだろう。副団長の任に就くというのに、君の邪魔にならなければいいのだが。」
「とんでもないことでございます、陛下。貴族でもなんでもない身寄りのない私が、姫様の婿を務めるなど恐れ多いことでございます。」
「そう謙遜することもなかろう。ここまで国が繁栄できたのは、護衛団の力でもあるし、それは君のおかげでもあるのだ。私も、娘の婿が最強の騎士であるというのは安心なことだ。」
「もったいないお言葉でございます。」
「バルドス、わがままな娘ですが、私たちの大切な1人娘です。よろしく頼みますね。」
「はっ!王妃様!バルドスのこの命に代えてお守りいたします!」
……この頃の私は、とても幸せだった。
ソルミナは小国ではあったが、国王も王妃も、そして民もがとても優しく穏やかだった。
国としての繁栄に向けた向上心はあったが、決して他国を脅かすような野心ではなく純粋な国としての成長を望んでおり、国内は活気と笑顔にあふれていたし、そんな国からの私への信頼も感じていた。
思い返すだけでとてもあたたかなものがこみあげてくる。
だが、そんな幸せも長くは続かなかった。
ヴァルグレア帝国の式典に招かれたその帰り、私たち一行は強大な魔物に襲われたのだ。
「魔物だ!!!」
「姫、馬車からお出になりませんように!!!!このバルドスが必ずお守りいたします!!!」
「ええ……お願いね。あなたも気つけて!」
「バルドス副団長!この魔物……魔法が効きません!!!」
「なんだと、下がれ!このバルドスの光の魔法剣で切り裂いて見せよう!!!」
「バカな…すべてはじき返されてしまうだと……!」
その魔物はとてつもない強さだった。おまけに光の魔法はまったく効かなかった。他の魔法や剣技を駆使して抵抗をするが、光の魔法剣に絶対的な自信を持ちそれだけを磨き続けてきた私には、他の手段など役には立たなかった。
(うん、すごいよ、バルドス。君は特別な子だね。でもその技にはあまり頼らないことだ。強すぎて剣技を磨くことに油断が生まれてしまう。剣は剣の技術として、魔法は魔法の技術として磨くことに専念しなさい。)
「そ……そうか……先生……そういうことだったのか……私は……間違っていたのですね……。」
魔物の猛攻を受け意識が朦朧とする中で、体を剣で貫かれ血と涙を流して地面に横たわるレイティアを私は視界にとらえた。
「レイ…ティア……」
「バル…ド……ス……」
「……んね……たく……のし……を……が……」
彼女は最後の力をふり絞って私を見つけると、私の顔を見てかすかに微笑み、私の名を呼び何かを口にしたのだ。
彼女があの場面で何を私に伝えたかったのか、知るすべもなく、私は意識を失ってしまった。きっとこんなにも頼りにならない私をとても恨んでいたのだろう。晴れ姿を国王や王妃に見せられなかったことに、私に罵声の一つでも浴びせたかったのだろう。
気づいたときには私はソルミナ王国の医療室にいた。
そこで護衛団が全滅したこと、レイティア姫も亡くなってしまったこと、私1人が奇跡的に生き延びてしまったことを聞かされた。
私は地獄のような苦しさに襲われた。護衛団の副団長という責任ある者が、自分の仲間も、自分の主の1人娘であり、自分の婚約者でもある大切な人も、誰1人守れず、自分だけ生き残ってしまったのだから。
結局それから国王と王妃に一度も顔を合わせることなく、私は護衛団の解任を聞かされた。
当然だろう。
寧ろ極刑でもしかるべきだっただろうに、あの優しい国王と王妃は私を直接的には責めることはなかった。
傷が治った私はソルミナ王国を1人静かに去った。
それから数か月、どこともいわずさまよった私は、ある時立ち寄った町の酒場でソルミナ王国が他国に侵略され滅びたことを知った。
ほんの、わずか数か月で私はすべてを失くしてしまったのだ。
大切な人も、迎え入れてくれる国も、私を包んでくれたあのあたたかさも。一瞬にしてすべてが消えてしまったのだ。
私は自分の無力さと傲慢さを憎み、魔物を恨み、他国の野蛮な人々を呪った。
そして、このバルドスの大切なものが二度と奪われない国を作ろうと、レイティアが望んだ笑顔の絶えない国を作ろうと心に誓い、バルドティア王国を建国したのだ。
私は剣術と魔法を一から磨き、さらに強さを求めた。そして同じ魔物に襲われても対処できる力を得た。バルドティア王国は力はもちろん、法律と秩序を重んじ、いかなる不正も野蛮な心も許さなかった。
絶対的な正義の元、国はみるみるうちに発展を遂げていった。
私は建国してから剣技に磨きをかけ続けた。国王であると同時に最強の騎士であり、最強の軍師であり続けたのだ。
騎士たちの戦力を上げるため、無意識に使っていた光の魔法剣を苦労の末体系化させ有能な騎士にのみ伝達し、軍の強さを盤石なものにした。
そして私がバルドティアを建国して17年の時が過ぎたそんなある時だった。
3人の子供が騎士に連れていかれ牢に入れられるところを目撃したのだ。
私はその騎士に訊ねた。
「このような幼い子供たちはなぜ牢に入れられているのだ?」
「はい国王陛下。この者たちの親は罪人であり、この者たちはその子供です。盗みを働いた者をその場で切り伏せたところ、この子供らが抵抗してきたため捕えました。
それに罪人の子供には罪人の危険因子がありますので、今のうちに対処しておかねばなりません。ご安心ください。この者たちは厳重に処罰いたします!」
(なんだと……?何かが……何かがおかしい……)
私はその言葉に急に不安を覚え、民の元に足を運んだ。
民に紛れその生活を目の当たりにし、私はとてもショックを受けたのだ。
「ばかな。民が……誰も笑っていない……!?」
そこに広がる光景は、闊歩する騎士に怯え、懐疑的なまなざしと疲れた表情で、けだるそうに生活する民たちの姿だった。
私はすぐに旅人に扮し、民にその暮らしを問いただした。
「そこの方、私は旅の者だ。ちょっと訊ねたいのだが、ここの暮らしはどうだ?初めてこの国に訪れたのだが、みな元気がなさそうに見える。」
「旅の人かい、あんたも早くここを離れたほうが身のためだ。いつ捕まるかわからないよ。この国は人の命よりも、厳しい法律のほうが大事だからね。ここに住んでいるか、旅で訪れているかなんて関係がないんだ。私たちもただただ、毎日怯えて生きてるだけだよ。自分が何か法をおかしていないか、騎士たちに見られていないかばかりが気になって、安心して日常生活なんて送れやしない。魔物に襲われない国だからってせっかくこの国に移り住んできたってのに、まるで囚人にでもなったような気分だよ。」
私は愕然とした。
魔物にも他国にも脅かされない、安全で平和な国を作りたかったのに、自国の人々の心の安全は守れていなかったのだ。レイティアが望んだ笑顔の絶えない国とは真逆であったのだ。
私は城に戻り、大臣たちを問い詰めた。
「なぜ我が国の民は笑っておらぬのだ?なぜこんなにも疲れて怯えた顔をしておるのだ?」
「陛下、まさか民のもとに足を運ばれたのですか!?どうかそのような行動はお控えいただけませんでしょうか。もし陛下に何か不敬を働いた者がいましたら、全員が極刑でございますよ。」
その言葉に愕然とした。
おそらく、大臣たちに悪気はないのだ。そしてこの国の政治そのものが、この大臣たちのように歪んだ正義を振りかざしているのだろう。
「違う……違う、こんなのじゃない!!私が望む国の形はこうではないのだ!!!」
それから私は国の改革に取り組んだが、そのいびつな正義と法律は私の立場をも凌駕していた。何度も試行錯誤を繰り返すうちに私の心は疲弊し、こんな国にした自分を悔やみ、憎んだ。
「力こそ強大になった我が国ではあったが、私が幸せを感じたあの小国のあたたかさには到底及ばない。レイティア、君の言ったとおりだ。強さは幸せではないのだ。私は、また間違えてしまったのか。」
とても疲れてしまった。
自分の人生を捧げ、走り続けてきたことの結果は、私とレイティアが描いたそれとは大きく異なるばかりか、それとは反対のものだったのだから。
それからの私は抜け殻のように生きていた。
後悔し、何度も何度も自分を責め、自分を憎んだ。
そして自らの命を終わらせることを決めた。
疲れてしまったのだ。
あのあたたかい、国王と王妃、レイティアのもとに早く行きたいと心から願うようになった。
いや、もし仮にそんなことをしても、私のせいで苦しんでしまった国王や王妃に顔向けできないことはわかっていた。私は今の状況からただただ逃げたかったのだろう。
国を出てさまよった私はゴストナ渓谷にいた。
どうして、どのような道をたどってたどり着いたのかも、私の記憶になかった。
そして私は自らの剣を自らに突き刺したのだ。
自らへの憎悪と、魔物や野蛮な人間への怨念が湧き上がる中、私の意識は薄れていったのだ。
そして……意識を取り戻した時には、ここで倒れていた。
いや、本当はかすかに意識はあったのだ。
魔物と化した自分の体、憎しみのままに数多の人間も魔物も見境なく切り刻み、自分をも切り刻み、憎悪の中に曖昧な意識を沈めていたのだ。
しかしその醜い愚行も、これでやっと終えられる。
この勇敢で、とても力のある2人の人間のおかげでようやく終止符を打てるのだ。
だが、バルドティアの民たちだけは守らねば。私が魔物になり、ここで命が潰えても民の暮らしは続いていくのだから。
「オねガいだ……わたしが魔物になっタことは……誰にも伝えナいでくれ……世界に、バルドティアが、魔物が作った国だと奇怪な目で見られてシマう……それデ苦しむのは我が民たちだ………………民に、罪はない……悪は……わたし一人なのだから……」
「……ああ、わかった。バルドティアの筆頭騎士である、このカノが心から誓おう。偉大なる建国者バルドス様の意思は、このカノが守ります。」
……これでいい。勇敢なバルドティアの騎士よ、感謝する。
いよいよ意識が薄れてきた……私は消えるのだな……
ああ……私の人生とはなんだったのか。
私は誰のために何ができたというのだ……。
レイティア……こうなってしまった今の私には、君の人生を奪った魔物と同じものになってしまった私には、その名を呼ぶ資格もない。
だがせめて……どうか……どうか、あの世で君に謝らせてほしい。
なんだ……眩しいな……あの剣士の剣だろうか……それともあの世の光だろうか……
「……バルドス……」
「……レイティア!?」
「バルドス、ごめんね……たくさんの幸せをありがとう。」
ああ……レイティア……
「…………あり……が…とう……」
Real Fantasy物語 勇者ジェミニの伝説 外伝 光と影の物語 完
勇者ジェミニの世界を形作る他の物語も是非覗いてみましょう。
Real Fantasy物語 勇者ジェミニの伝説 外伝 ~もう1つの英雄伝説~
*******************************************
Real Fantasy物語公式Xでは魔女の手記が公開されていますのでチェックしてみましょう。
今は失われた世界のかつての姿を知ることができます。
Real Fantasy物語公式Xはこちらから。